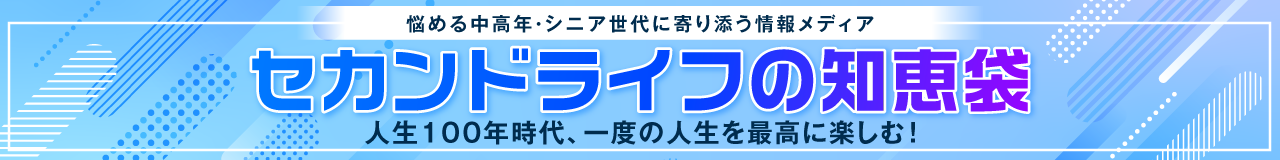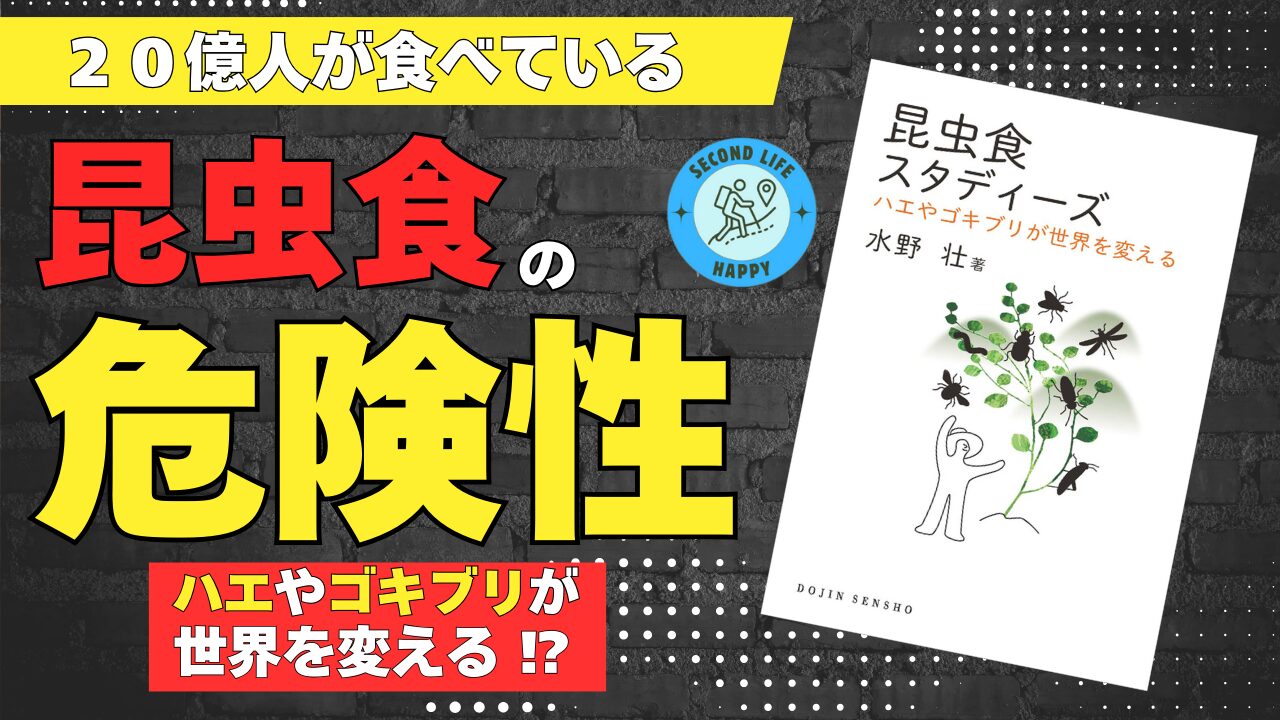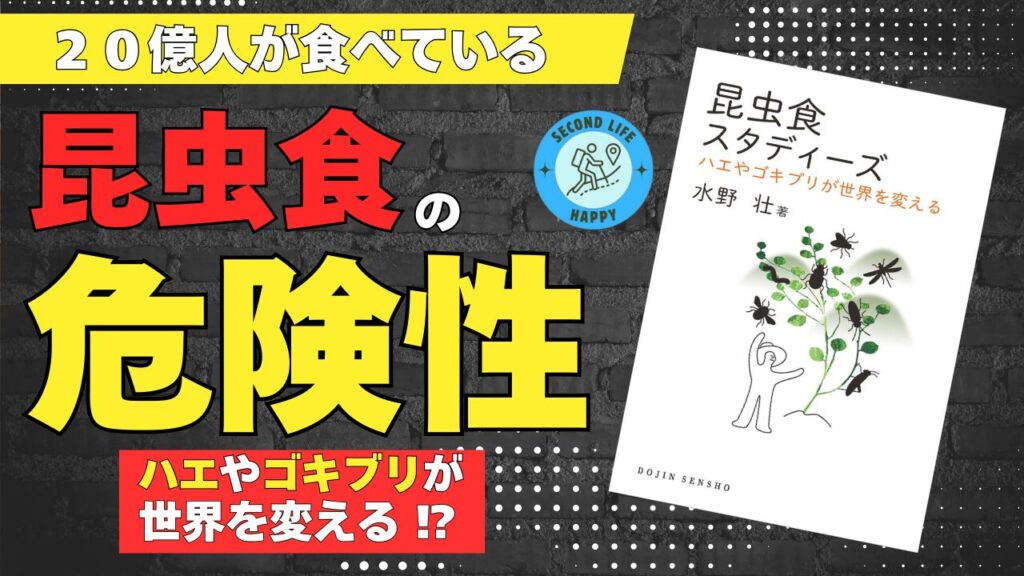
昆虫食「食わず嫌い」ではもったいない⁉︎

昆虫食」が新しい食のトレンドとして注目される一方で、「昆虫食は危険性があるのでは?」という漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。アレルギーや寄生虫、見た目の問題など、昆虫食に対する懸念は尽きません。
今回は、そんな昆虫食の危険性について、筆者の視点から深く掘り下げていきます。「食わず嫌い」だけで敬遠してしまうのはもったいないかもしれません。この記事を読めば、昆虫食の正しい知識と、安全に楽しむためのポイントがわかります。
- 参考書籍:『昆虫食スタディーズ』 著:水野 壮 出版:2022年 2月25日
- 私自身、この記事を執筆するにあたって、この本を参考にしました。この本は、単に「虫が食べられるか」という話だけでなく、昆虫の栄養価やアレルギーのリスクといった科学的な側面に加え、歴史や地球環境への影響、そしてビジネスとしての可能性まで、多角的に昆虫食を解説しています。
- この本が昆虫食に対する漠然とした不安を、科学的な根拠に基づいた具体的な知識へと変えてくれる点です。例えば、アレルギーの原因となるタンパク質の話や、養殖環境が安全性をどう担保するかといった説明は、読者が抱える疑問に直接的に答えてくれます。
昆虫食は決して「新しい文化」ではない

昆虫食の危険性について議論する前に、まず知っておきたいのは、昆虫食が決して突飛なものではなく、古くから人類の食文化に根付いてきたということです。
国連食糧農業機関(FAO)の報告書によると、現在、世界では20億人以上が昆虫を食べていると言われています。特に、タイ、メキシコ、中国などのアジアや中南米の国々では、昆虫は古くから食卓に上る身近な食材です。
世界の現状:20億人が食べている「身近な食材」
これらの地域では、昆虫を揚げる、炒める、煮込むなど、様々な調理法で美味しく食べられています。また、近年では欧米でも、昆虫をプロテインバーやパウダーに加工した商品が登場し、地球温暖化や食料危機への対策として注目されています。昆虫食は、まさにグローバルな食の選択肢となりつつあるのです。
日本の現状:郷土料理として受け継がれた「命の恵み」
日本にも、昆虫食の歴史があります。代表的なものに、長野県や岐阜県などの山間部で食べられてきたイナゴの佃煮や、ハチノコの甘露煮などがあります。これらは、貴重なタンパク源として、あるいは保存食として、人々の生活に深く根付いてきました。
昆虫は、私たちの祖先が飢えをしのぎ、命をつないできた「命の恵み」だったのです。
昆虫食の危険性:なぜ懸念されるのか?

昆虫食が世界中で食べられているとはいえ、やはり私たちは「未知のリスク」に敏感になります。ここでは、昆虫食が危険視される主な理由を、一つひとつ丁寧に見ていきましょう。
1. アレルギー:甲殻類アレルギーとの関連性
昆虫食で最も注意すべきリスクの一つがアレルギーです。昆虫は、エビやカニなどの甲殻類と遺伝的に近い種が多く、共通のアレルゲン(トロポミオシンというタンパク質)を持つことがわかっています。
そのため、甲殻類アレルギーを持つ人は、昆虫食によってアレルギー反応を起こす可能性が高いと考えられています。初めて昆虫食を試す際は、甲殻類アレルギーの有無を必ず確認し、少量から試すことが大切です。
2. 寄生虫:市販品と天然物でリスクは違う?
「虫を食べるなんて、寄生虫が怖い!」と考えるのは当然です。寄生虫による感染リスクは、特に生食や不十分な加熱処理をした場合に高まります。
しかし、市販されている食用昆虫のほとんどは、衛生管理が徹底された施設で養殖されており、加熱処理も施されているため、このリスクは極めて低いと言えます。
一方で、自分で捕獲した天然の昆虫を食べる場合は注意が必要です。天然の昆虫には、どのような寄生虫がいるかわかりません。十分に加熱(中心部まで火を通す)してから食べるようにしましょう。
3. 有害物質:重金属や農薬の蓄積
昆虫は、生息している環境中の有害物質(重金属や農薬など)を体内に取り込んでしまう可能性があります。例えば、汚染された土壌で育った昆虫は、鉛やカドミウムといった重金属を蓄積しているかもしれません。
このリスクを回避するためには、やはり信頼できる養殖業者から購入することが最も安全な選択です。市販の食用昆虫は、安全な飼料を与えられ、管理された環境で育てられています。
「食べてはいけない昆虫」を見分けるポイント
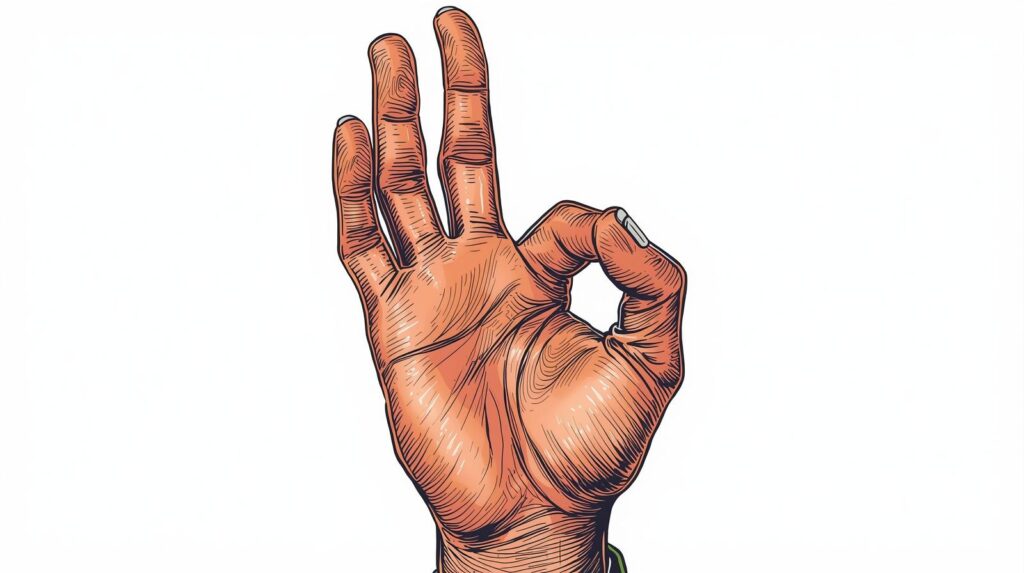
もし自分で昆虫を採集して食べたいと考えるなら、安全な昆虫と危険な昆虫を見分ける知識が不可欠です。
- 毒を持つ昆虫: 毒を持つ代表的な昆虫として、タガメ、セミ、カミキリムシなどが挙げられます。これらの昆虫は、捕食者から身を守るために毒を持っています。
- 有毒植物を食べている昆虫: 毒性を持つ植物(例えば、キョウチクトウなど)を食べることで、その毒が昆虫の体内に蓄積されることがあります。モンシロチョウの幼虫(アオムシ)や、テントウムシの一部がこれに該当します。
- 派手な色の昆虫: 派手な色や模様を持つ昆虫は、しばしば毒や不快な味を持っていることを示しています。これは「警告色」と呼ばれ、捕食者に「食べないで」と訴えかけているのです。
安易に採集して食べることはせず、専門家や信頼できる情報源を参照するようにしてください。
安全に昆虫食を楽しむためのチェックリスト
昆虫食の危険性について、正しく理解すれば、過度に恐れる必要はありません。最後に、安全に楽しむためのチェックリストをご紹介します。
- 信頼できる販売元から購入する: 衛生管理が徹底された養殖業者や、食用昆虫専門店などから購入しましょう。
- アレルギーの有無を確認する: 特に甲殻類アレルギーを持つ人は、少量から試すか、専門家に相談しましょう。
- 十分な加熱処理を行う: 寄生虫や細菌のリスクを避けるため、中心部までしっかりと加熱してください。
- 加工食品から試す: 抵抗がある場合は、昆虫パウダー入りのクッキーやプロテインバーなど、加工食品から試してみるのも一つの手です。
昆虫食の未来と安全性:最新の取り組み

昆虫食の安全性確保に向けた研究は、日々進んでいます。食品としての基準を定め、アレルゲンや有害物質の検査方法を確立する動きも加速しています。
昆虫食は、単なる好奇心を満たすものではなく、地球の未来を支える可能性を秘めた食材です。正しく理解し、賢く付き合うことで、私たちの食生活はさらに豊かになるでしょう。
あなたがこの記事を読んで、昆虫食への不安が少しでも和らぎ、新しい食の選択肢に目を向けるきっかけとなれば幸いです。